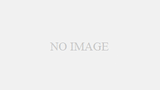今回は中野信子著書「不倫」を紹介したいと思います。
不倫 (文春新書 1160) | 中野 信子 |本 | 通販 | Amazon
中野信子さんの本は、いつも面白く読んでいるため、「不倫」という一見 手に取らないような本を読んでみることにしました。
私自身、不倫をしたことはありませんが、周りを憚らず不倫をしている人を何人も知っており、その心理に興味を持っていたため、この本を手に取りました。
ただ、移動中や休憩時間など、あまりタイトルを見られないように意識して読了しました。
もちろん、本の内容は「恋愛小説」や「エッセイ・体験記」ではなく、中野信子さんらしく、客観的、エビデンスをもって淡々と書かれています。
「不倫はなくならない」科学的な理由
冒頭、結論を伝えているのですが、
「人類社会において不倫がなくなることはおそらくない」
理由は、
「私たちは遺伝子や脳内物質に操られている、人類の歴史をみても一夫一婦制が厳格に守られたことはない。」
一夫多妻や乱婚を許容してきた社会集団のほうが、人口維持に有利に働くのは想像に及ぶところだと思います。
一夫一婦制のプレーリーハタネズミのメカニズム
一夫一婦制をとる哺乳類は全体の3~5%しかおらず、その中でも有名なのがプレーリーハタネズミです。
一度つがいになると終生添い遂げ、パートナーが死んでも他の異性を避けるという忠誠ぶりを見せます。
実は、脳内ホルモンによって行動が決まることが説明されています。
交尾の際にオスの脳内で分泌される「アルギニンバソプレシン」は、家族を守るよう動機づけるホルモンです。プレーリーハタネズミはこのホルモンの受容体密度が高いため、影響を強く受けるそうです。
※ホルモンの受容体密度が高いと、そのホルモンの影響を受ける。
ホルモンの受容体密度が低いと、そのホルモンの影響は受けにくい。ホルモンの量ではない!)
このホルモンの投与や阻害によって、実際に性行動が変化することが実験で確認されています。
人間でもアルギニンバソプレシンを投与することで、性的刺激への反応が強まるという研究もあるそうです。
つまり、性行動すら脳内の物質やその個体の受容体密度によってある程度コントロールされていることが示されています。
不倫しやすい人は遺伝子で決まる?
そして、
人間の場合、ある特定の塩基配列によって「不倫傾向」が高いタイプと、逆に「貞淑型」に分類されるタイプが存在し、その割合は、おおよそ「5:5」だと推測されています。
(AVPR1A遺伝子の塩基配列によって違うようです。アルコールの分解酵素があるかないかも同じ理屈)
不倫しやすいのか、しにくいのかは、遺伝子の影響を受けることが分かりました!
乳幼児期の養育者との関りも影響する?
遺伝子のほかに影響するものがあります。
それは、乳幼児期の養育者との関係性によって、その後の人間関係に大きな影響を及ぼします。
例えば、
赤ん坊の泣き声に対してすぐに愛情をもって反応する養育者は子供に安心感を与えます。
呼べばすぐに応えてくれる「安全基地」という存在があることで、安心して探索行動を取れたり、自立した行動を取れるようになる。
他者を良いものと捉えて積極的に関われる「安定型」の人間になると考えられています。
逆に、
養育者に構ってもらえなかった場合は、「期待できない」と学習してしまい、探索行動は及び腰になり、人との関りを避ける傾向になってしまいます。
かまってもらえずに失望したり、拒絶されて傷つくことがないように学習すると考えられます。
こうして育った場合、「回避型」や「不安型」の人間になり、
「回避型」は恋愛を面倒と捉え、軽い関係を求めてしまう
「不安型」は愛情を性行為で確かめようとし、多くの異性と関りを持ちやすいようです。
これら傾向は、個人の責任というとよりも養育環境に強く結びつくことが分かります。
「安定型」に近づく方法はあるのか?
この本では、「回避型」や「不安型」に対して「安定型」に近づく方法も示しています。
愛着スタイルを変化させるという目的で、「安全基地」のような存在と一緒にいることで、その影響を受けることができる、としています。
「この人がいると空気が穏やかになる」「失敗しても責められないような雰囲気をつくる人」
そんな人が、そばにいると「安定型」の影響を受け人間関係を良いものと認識されるんだと思います。
まとめ
以上、ざっくりですが、紹介させていただきました。
不倫をしやすいかどうかは、遺伝子や養育環境に影響を受ける。
ただし、「安定型」の人と一緒にいることで人間関係の考え方(愛着スタイル)が変わる可能性がある。
ということでした。
感想
本記事では深堀しませんでしたが、「安定型」「回避型」「不安型」の違いについても一章を割いて記載しています。
個人的にはこの章が面白く、自分の友人・知人に照らし合わせて理解したりしていました。
また、愛着形成の章も興味深く、幼少期の親子関係の大切さを知り、それが上手くいかなかったとしても取り戻せることを知りました。
中野信子さんの著書は、どれも読みやすく論文や数値、実際の出来事など根拠を持って説明してくれています。
新刊が出ると、つい手に取ってしまう著者の一人です。
皆さまも、ぜひ、手に取って読んでみてください。